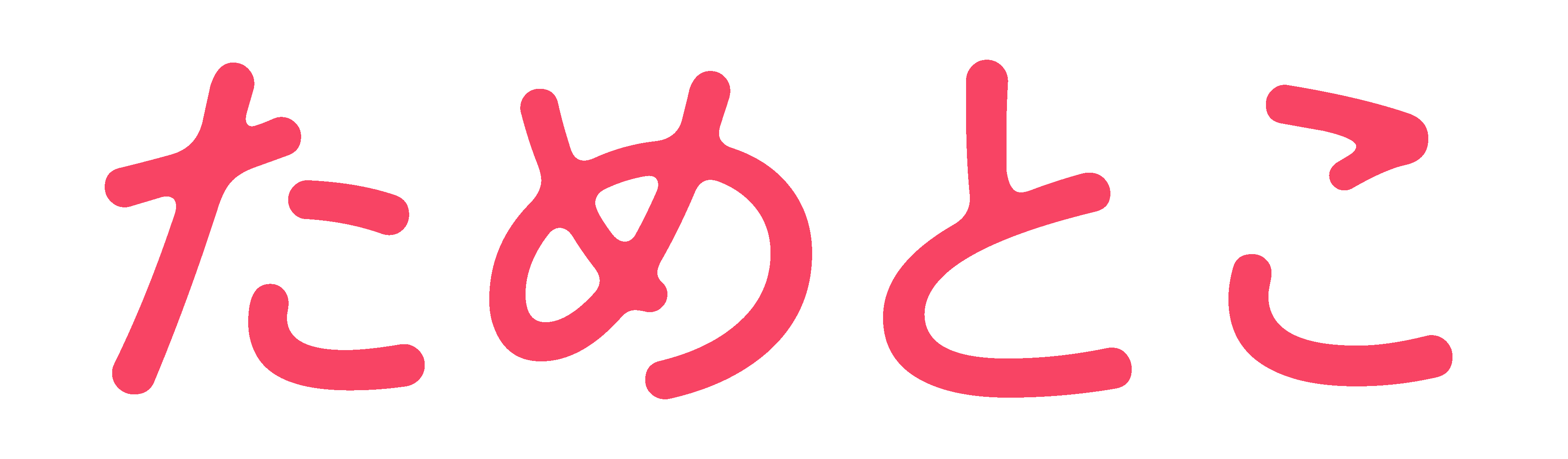薬剤師が知っておきたい災害時の薬局の防災対策とお薬手帳の活用法
2025.08.27

毎年9月1日は「防災の日」。1923年の関東大震災をきっかけに制定され、全国で防災訓練や備蓄の見直しが行われています。薬局にとっても、防災の日は体制を再確認する絶好のタイミングといえるでしょう。
地震や台風などの自然災害は、いつどこで起こるかわかりません。そんな中、地域の薬局は医薬品の供給拠点であり、住民の健康を守る重要な役割を担います。災害時に迅速かつ適切な対応を行うためには、日頃からの防災対策が不可欠です。
本記事では、防災の日にあわせて見直したい薬局の役割やお薬手帳の活用方法、備えておくべき医薬品や物資、そして災害に強い薬局づくりのポイントをご紹介します。
目次
災害時に薬局・薬剤師が果たす役割
災害が発生すると、医療体制は一気に逼迫します。そんな中でも、薬局は地域の医薬品供給や服薬指導を担い、住民の生活と健康を支える存在です。避難所や医療機関と連携し、限られた資源の中で必要な薬を届けるための体制づくりが求められます。
地域住民の健康と医薬品供給を守る拠点として
災害が発生すると、医療機関の受診が困難になり、薬の供給体制も不安定になります。こうした状況下で、薬局は地域住民の健康を支える拠点として重要な役割を果たします。求められるのは、必要な医薬品の確保と的確な供給です。限られた在庫の中で優先順位を判断し、必要な患者に確実に届けることです。
特に持病を抱える患者や高齢者は、薬の中断が命に関わる場合があります。血圧降下薬や糖尿病治療薬など、日常的に服用している薬が途切れないよう、患者ごとの服薬状況を把握し、継続的な支援を行うことが重要です。
災害時には、頭痛や胃腸の不調、かゆみといった軽い症状を訴える住民が薬局を訪れるケースも少なくありません。こうした場合、薬剤師がOTC薬等を適切に提案し、あわせて生活習慣やセルフケアの工夫を助言することは、医療機関の混雑を和らげる大きな力になります。薬局が果たす役割は単なる医薬品供給にとどまらず、地域医療の一端を支える拠点として、住民の安心と健康を守る存在へと広がっていくのです。
避難所や医療機関との連携体制を整え
災害時には、医薬品や物資の確保が課題となります。そのため、平時から地域の医療機関、自治体、避難所との連携体制を構築しておくことが欠かせません。具体的には、緊急時の連絡先一覧や搬送ルートの共有、役割分担の事前確認などです。
また近隣の薬局や病院と協力し、在庫や必要物資の情報を共有することで、効率的な供給が可能になります。地域の防災訓練や会議への参加も、顔の見える関係づくりに有効です。事前のつながりがあることで、混乱時にも迅速かつ的確な連携が実現できます。
災害時に役立つお薬手帳の活用法
お薬手帳は、災害時に患者の安全を守る「命綱」ともいえるツールです。かかりつけ薬局や医療機関が利用できない状況でも、過去の服薬履歴やアレルギー情報を正確に伝えることで、適切な薬の処方や治療につながります。
特に避難所や初めて受診する医療機関では、患者自身の健康情報を伝えるための唯一の情報源となる場合もあります。日頃から「いざという時に役立つ」準備をしておくことが、薬剤師にとっても患者にとっても大切です。
正確な服薬情報を伝えるための重要ツール
実際の災害時には、患者本人の記憶だけでは薬の種類や用量を正確に伝えきれないことも少なくありません。そこで役立つのがお薬手帳です。
日頃からお薬手帳を活用し、現在服用している薬や過去の処方歴、アレルギー、持病といった情報が体系的に整理されていれば、避難所や他地域の医療機関でも処方をスムーズに行うことができ、薬の重複や飲み合わせによるトラブルを未然に防ぐことができます。
日頃から患者に持参を促す声かけと工夫
お薬手帳を持っていても、普段から携帯していない人は少なくありません。薬剤師は来局時に「災害時にも役立ちますので、普段から持ち歩きましょう」と声をかけることが大切です。紙媒体に加え、スマートフォンアプリなどの電子版も併用すれば、紛失や忘れを防げます。定期的に情報を更新するよう促すことも忘れないようにしましょう。
薬局が備蓄しておくべき防災用医薬品・物資
災害時には、一般用医薬品や衛生用品の需要が急増します。解熱鎮痛剤や整腸剤、消毒液、生理用品など、生活や健康を守るために欠かせない物資を事前に備蓄しておくことで、地域への迅速な支援が可能になります。
災害時に需要が高まる一般用医薬品の例
災害後は、体調不良や持病の悪化を訴える人が増えます。解熱鎮痛剤、整腸剤、便秘薬、抗アレルギー薬、外用消炎鎮痛薬など、幅広い症状に対応できるOTC薬を用意しておくことが重要です。特に小児用や高齢者向けの製剤も備えることで、幅広い年齢層に対応できます。
衛生環境を守る生活必需品の備蓄
避難生活では衛生環境が悪化しやすく、感染症のリスクが高まります。マスク、消毒液、石けん、ウェットティッシュ、生理用品、手袋、ガーゼ、包帯などを十分に備蓄しておくことが重要です。これらは二次的な健康被害を防ぎ、避難生活の質を守るためにも欠かせません。
災害に強い薬局づくりとBCPの重要性
災害時も業務を継続するためには、BCP(業務継続計画)の策定と定期的な見直しが欠かせません。さらに、緊急時にスタッフ全員が同じ行動を取れるよう、連絡手順や訓練体制を整えることが混乱を最小限に抑え、薬局としての機能を維持する鍵となります。
BCPの策定と定期的な見直し
BCPでは、災害発生時にどの業務を優先するか、誰が何を担当するかを明確にします。薬や機器、非常用電源などの確保方法、代替手段も盛り込みます。計画は作成しただけで終わらせず、年1回以上の見直しと更新を行い、現状に即した内容に保つことが重要です。
緊急時に迷わないための連絡手順と訓練体制
災害時に迅速な対応を行うためには、連絡網や行動マニュアルを整備し、緊急時の連絡先や優先順位、報告ルートを明確にしておく必要があります。さらに、定期的な避難訓練を実施し、実際に動いてみることで改善点を洗い出します。訓練後の振り返りと共有が、確実に機能する体制づくりにつながります。
まとめ
防災の日は、薬局にとっても備えを見直す大切な節目です。この機会に、備蓄品やお薬手帳の案内、BCPの内容を再確認しておくことで、いざという時に迷わず行動できる体制が整います。薬局は平時から地域医療の重要な拠点であり、日頃の取り組みが非常時に地域の安心と健康を守る力となります。
薬剤師の生涯学習を支援するための単位管理アプリです。
最短5分から学習できるコンテンツのほか、
研修認定薬剤師の取得済み単位シールや、
単位証明書の登録による、便利な単位管理システムも備えています。
詳しくはこちら!