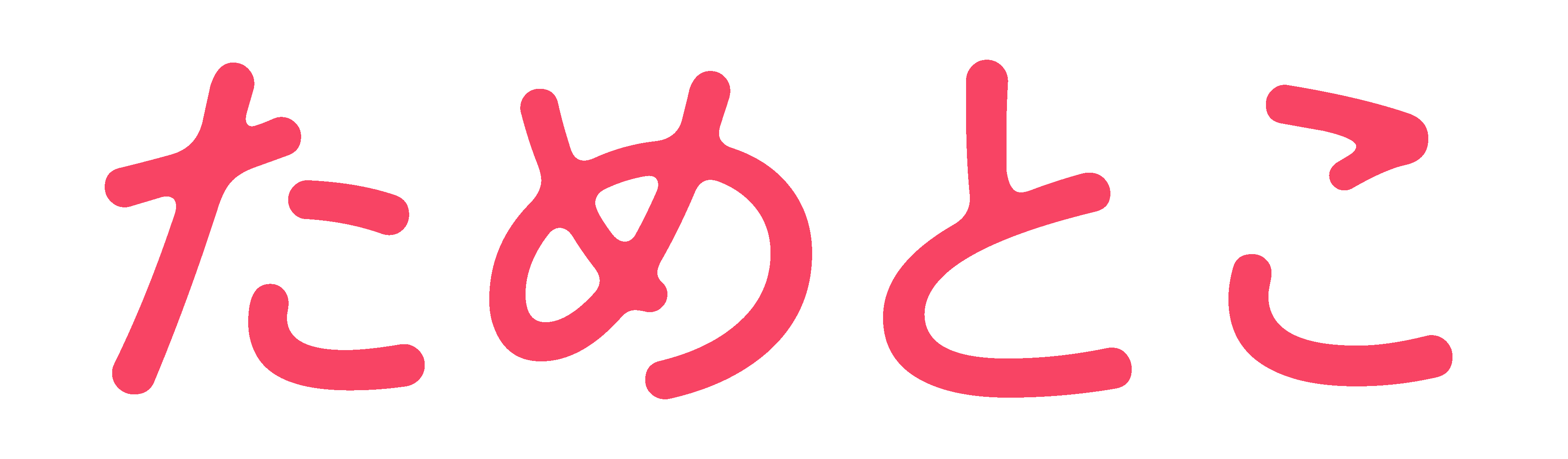精神科患者との接し方|薬剤師のためのコミュニケーション術
2025.10.08

精神疾患を抱える患者さんと接する際、「どう声をかければいいのか分からない」「話がかみ合わない」と戸惑う薬剤師は少なくありません。処方箋だけでは患者の背景が見えづらく、コミュニケーションに不安を感じることも多いでしょう。
本記事では、精神疾患を持つ患者さんの特徴や、現場で活かせる具体的な対応のコツを整理します。小さな意識の積み重ねが、服薬指導や信頼関係の構築につながります。
目次
精神疾患を抱える人の特徴とは
精神疾患患者の特徴として代表的なものは下記の5つです。
- 返答が遅い・会話が途切れる
- 表情が乏しい・感情の起伏が少ない
- 話がかみ合わない・唐突な発言がある
- 同じ質問を繰り返す・不安が強い
- 会話を避ける・沈黙が多い
これらは必ずしも「非協力的」という意味ではなく、疾患特性やそのときの心理状態に由来するものです。例えば、うつ病では思考や反応が遅くなることがあり、統合失調症では幻聴や妄想の影響で会話がかみ合わないことがあります。双極性障害では気分の波によって饒舌な時期と沈黙になりがちの時期が極端に分かれることも。不安障害では緊張や過度な心配から、同じ質問を繰り返すケースもあります。
薬剤師はこうした行動を「協力してくれない態度」と決めつけるのではなく、疾患の一部として理解する姿勢が大切です。外見や短いやり取りだけで判断せず、患者のペースを尊重することが信頼関係構築の第一歩につながります。
精神疾患を抱える人とのコミュニケーションの留意点
- 相手の主張を否定しない
- あせらず時間を共有する
- 疾患特性を理解しておく
- 相手の表情や仕草に注意を払う
- 丁寧な言葉遣いを意識する
これらはすべて「安心できる環境をつくるための基本姿勢」といえます。精神疾患のある患者は、否定的な言葉や急かされる態度に敏感に反応しやすく、わずかな違和感で不安が増してしまうこともあります。
薬剤師が意識すべきなのは、正しい知識を持ちながらも、観察と配慮を通じて「寄り添う姿勢」を示すことです。命令的ではなく柔らかい依頼形で話す、返答のテンポを待つといった小さな配慮が、患者さんに「安心して相談できる存在」と感じてもらう土台になります。
医師や看護師、専門家との連携
精神科領域では、薬剤師だけで対応できる範囲には限界があります。そこで重要になるのが、医師や看護師、精神保健福祉士など専門職との連携です。
患者の服薬状況や日常の変化で気になる点があれば、速やかに共有することが求められます。特に、自殺念慮が疑われる発言や躁転の兆候が見られる場合は、迅速に医師へ報告する必要があります。
また、薬剤師が地域連携の中で患者をサポートできる場面も増えています。患者のメンタル面を支えるために、自分一人で抱え込まず、チーム医療の一員としての視点を持つことが重要です。
すぐに実践できる!コミュニケーション技法3選
日常の業務ですぐに活用できる、シンプルなコミュニケーション技法を紹介します。小さな工夫でも、患者に与える印象は大きく変わります。
ミラーリングとペーシング
患者の姿勢や呼吸、声のトーン、話すスピードに自然に合わせる方法です。たとえば、患者が小声でゆっくり話しているなら、こちらも少しペースを落として柔らかい声で返すことで「同じリズムで会話できている」という無意識の安心感を与えられます。
逆に、患者が早口で不安を訴えている場合は、少しテンポを合わせつつ、徐々に落ち着いたスピードに誘導すると、自然と安心を与えることができます。過度に真似をすると不快感を与えるので、あくまでさりげなく取り入れるのがポイントです。
バックトラッキング
相手の発言をそのまま繰り返したり、要約して返す方法です。「薬を飲むと眠くなって困るんです」という訴えに対して「眠気がつらいのですね」と返すだけでも、「自分の話を理解してもらえた」と患者は感じます。
特に精神疾患の患者は「否定されるのでは」という不安を抱きやすいため、この技法は安心感を高めるうえで有効です。また、バックトラッキングを続けると患者自身が話を整理しやすくなり、より詳しい情報を引き出すことにもつながります。
オープンクエスチョン
「はい・いいえ」で答えられる質問ではなく、「どんなときに症状が強く出ますか?」「薬を飲むときに不安を感じる場面はありますか?」といったオープンな質問を使うことで、患者の状況や思いを深く知ることができます。クローズドな質問では得られない具体的な背景情報を引き出せるため、服薬指導の質が上がります。
ただし、一度に多くの質問を投げかけると負担になるため、短くシンプルに一つずつ聞き出す姿勢が大切です。
まとめ
精神疾患を抱える患者への対応は、薬剤師にとってハードルが高く感じられることがあります。しかし、否定せずに受け入れる姿勢、時間を共有する余裕、観察を交えたコミュニケーションといった小さな工夫で、大きな変化を生むことができます。
また、医師や看護師など専門職と連携することで、より質の高いサポートが可能になります。完璧を目指す必要はなく、まずは「安心感を与える存在」として信頼されることが、服薬継続や治療効果の向上につながるでしょう。
薬剤師の生涯学習を支援するための単位管理アプリです。
最短5分から学習できるコンテンツのほか、
研修認定薬剤師の取得済み単位シールや、
単位証明書の登録による、便利な単位管理システムも備えています。
詳しくはこちら!