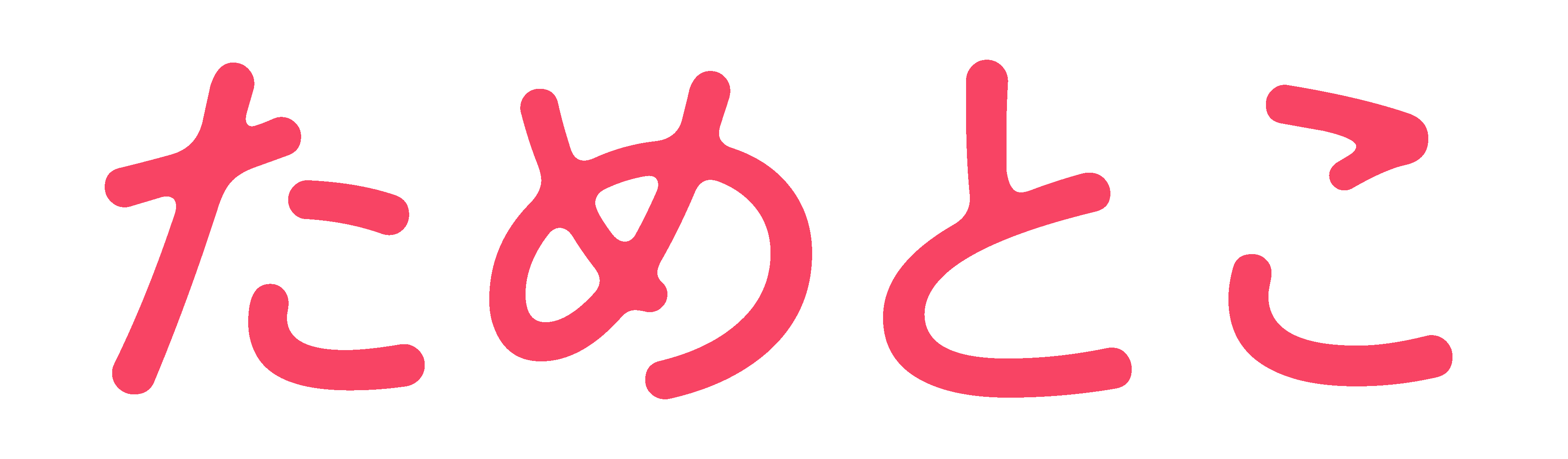薬局のカスハラの実態とその対応策
2025.09.04

薬局やドラッグストアでは、患者さんからの理不尽な要求や暴言といった「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が問題になっています。厚生労働省の調査でも、勤務先でカスハラを経験した人は約1割にのぼり、薬局でも深刻さを増しています。
本記事では、薬剤師が直面しやすいカスハラの実態や事例を紹介し、遭遇した際の対応ポイントや薬局としての防止策を解説します。
目次
カスタマーハラスメントの現状
近年、薬局やドラッグストアでも「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が深刻な課題となっています。厚生労働省が令和6年に発表した調査によると、過去3年間に勤務先でカスハラを経験した労働者は約1割。これは医療業界も例外ではなく、日本薬剤師会が同年9月に実施した調査では、弁護士や専門窓口への相談が必要だと感じた苦情やクレームが、直近2年間に約3割の薬局で発生していました。
薬局は地域に密着した医療提供の場であり、患者さんにとって最も身近な存在です。しかしその「距離の近さ」が、時に不当な要求や暴言といったハラスメントにつながることがあります。薬剤師自身の精神的負担だけでなく、現場の雰囲気やサービスの質にまで影響を及ぼすため、組織的に対応していくことが求められています。
薬局におけるカスハラとは
カスハラとは、顧客から従業員に対して行われる暴言・脅迫・理不尽な要求・過剰なクレームなどを指します。薬局の場合、以下のような具体例が挙げられます。
- 服薬指導中に「こんな説明は不要だ」「早くしろ」と怒鳴られる
- 待ち時間に不満を爆発させ、大声を出したり机を叩いたりするなど威圧的な態度をとる
- 長時間にわたり同じ内容を繰り返し訴えて拘束する
こうした行為は、業務を妨害するだけでなく、薬剤師やスタッフのメンタルヘルスにも大きな悪影響を与えます。
顧客トラブルが増加したわけ
カスハラが増加傾向にある背景には、いくつかの社会的要因があります。
- コロナ禍以降の不安感や苛立ち:マスク着用や検査キットの販売対応で薬局への要求が集中した
- 患者の権利意識の高まり:医療サービスを「顧客サービス」と混同し、過剰に要求するケースが増加
- 待ち時間や人員不足の影響:混雑時のストレスが薬剤師へのクレームにつながりやすい
- SNSでの拡散リスク:不満をその場だけでなく、口コミサイトやSNSで公開するケースも
こうした要因が複合的に重なり、薬局におけるカスハラ件数は増加しているのです。
薬局で起きたカスハラの事例
カスハラの深刻さを理解するには、具体的な事例を知ることが重要です。薬局で実際に起きているケースを整理すると、以下のような傾向が見られます。
順番待ち中の威圧的な言動と薬剤師への暴言
調剤薬局では「急げ」「早くしろ」と威圧的な発言をする顧客がいます。服薬指導を始めると暴言を浴びせるケースもあり、説明の妨げとなり誤解や服薬トラブルのリスクを高めます。こうした場面では、冷静さを保ち複数人で対応することが重要です。
処方外薬剤を要求し「殺すぞ」と脅迫
処方外の薬を求め、断られると「殺すぞ」と脅す事例もあります。これは業務妨害や安全を脅かす重大なカスハラで、即時の記録と上司・関係機関への報告が欠かせません。
長時間拘束や過度な問い合わせ
同じ内容を繰り返し訴え、カウンターを長時間占有する行為もカスハラの一種です。他の患者の対応ができなくなり、業務全体の遅延やスタッフの疲弊につながります。
SNSや口コミサイトでの誹謗中傷
直接的な暴言に限らず、SNSや口コミでの悪評も深刻です。 reputational damage(評判被害)につながり、組織全体に長期的な影響を与える可能性があります。
カスハラから身を守るポイント
薬局でのカスハラは、誰にでも起こり得るリスクです。大切なのは「感情的にならず、冷静に・安全に・組織的に」対応すること。ここでは薬剤師や従業員が自分を守るために押さえておきたいポイントを解説します。
冷静さを保ち、事実に基づいて対応する
カスハラでは相手の怒声や要求に動揺しがちですが、感情的に反応すると事態が悪化します。「規則上できない」「薬事法で決まっている」と事実に基づき、淡々と説明することが大切です。冷静な姿勢は相手の引き下がりを促し、無用な衝突を避けられます。
クレーム対応の基本
対応は「傾聴 → 共感 → 事実確認 → 解決策提示」の流れが基本です。
まずは相手の言葉を遮らず聞き取り、「ご不安にさせてしまったのですね」と共感を示します。その後、規則に基づく説明を行い、代替案やできる範囲の対応を伝えることで、感情的な対立を和らげられます。
記録(録音・メモ)を残しトラブルを可視化
暴言や脅迫を受けた場合は、録音や詳細なメモを必ず残しましょう。これにより上司や弁護士への相談が容易になり、エビデンスとしても活用できます。記録を組織で共有すれば、再発防止や対応力の向上にもつながります。
一人で対応しない
カスハラを一人で抱えるのは精神的にも危険です。できるだけ同僚や上司を呼び、複数人で対応しましょう。第三者が加わることで相手が冷静になることも多く、スタッフ側の安心感も高まります。「一人で対応しない」ということをルール化しておくと負担を分散できます。
薬局でできるカスハラ対策
カスハラを防ぐには、現場任せではなく「仕組み」として対策を整えることが大切です。ポスター掲示や対応ルールの明確化などを組み合わせることで、薬剤師やスタッフの安全と安心を守ることができます。
ポスターの活用
「迷惑行為はご遠慮ください」と掲示するだけでも、患者への注意喚起となりトラブル抑止に有効です。日本薬剤師会でもカスハラ防止ポスターを作成・公開しているため、参考にするとよいでしょう。
クレーム対応のルール化
クレーム一次対応を誰が行うかを明確化し、対応フローをマニュアル化することでスタッフの負担を減らすことができます。定期的な研修やロールプレイを通じて、チーム全体でスキルを共有することも効果的です。
外部の相談窓口・専門機関を活用する
カスハラ対応は一人で抱え込まず、労働局や薬剤師会、弁護士(法テラスなど)といった外部窓口を早めに活用しましょう。EAPや産業医がいる職場では、メンタル面の相談にも役立ちます。専門機関を頼ることで、精神的負担の軽減と再発防止につながります。
まとめ
薬局でのカスタマーハラスメントは増加傾向にあり、暴言や理不尽な要求は職場環境や医療サービスに悪影響を及ぼします。
対応には、個人の心構え(冷静さ・記録・複数対応)と組織的な対策(ポスター掲示、ルール化、研修)が欠かせません。 また、解決が難しい場合は労働局や薬剤師会、弁護士など外部機関を活用し、精神的負担を軽減することが重要です。薬剤師が安心して働ける環境を整えることが、患者への質の高い医療提供につながります。
参考文献
・厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査」
・厚生労働省「カスタマーハラスメント事例集」
・日本薬剤師会「カスタマーハラスメント防止啓発ポスターを作成しました」
もっと知りたいあなたへ!「ためとこ」で学べるカスハラ対策講座
カスハラ(カスタマーハラスメント)について、もっと深く知りたい方には「ためとこ」の講座がおすすめ!
カスハラから身を守るための対応を、弁護士がわかりやすく解説しています!
「知ってるつもり」を「ちゃんと対策できる」に変える第一歩、ぜひチェックしてみてくださいね!
薬剤師の生涯学習を支援するための単位管理アプリです。
最短5分から学習できるコンテンツのほか、
研修認定薬剤師の取得済み単位シールや、
単位証明書の登録による、便利な単位管理システムも備えています。
詳しくはこちら!